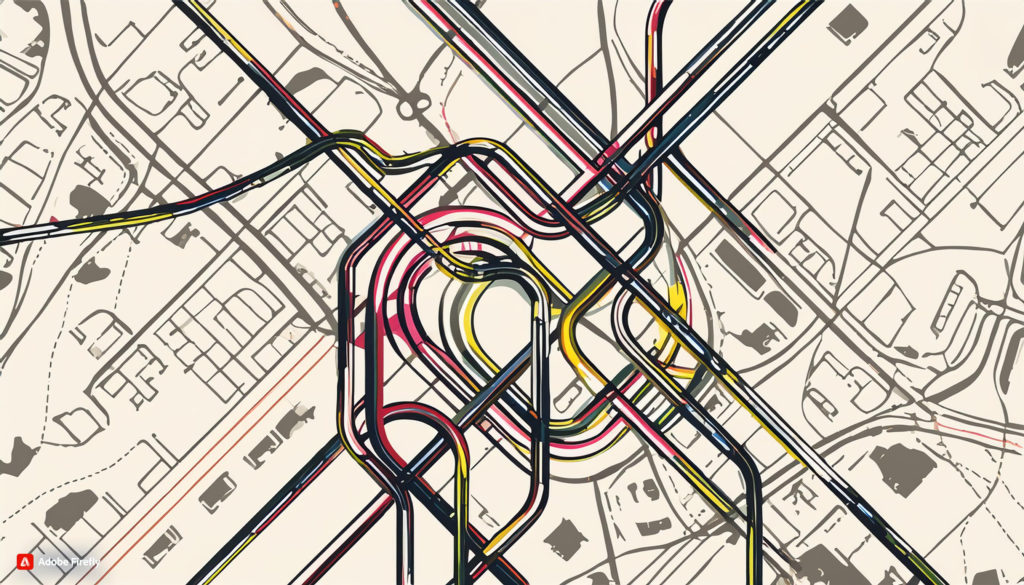
SUMMARY
特撮は今日、第1次怪獣ブームと第2次怪獣ブームという二度の隆盛期を経験したジャンルとして認識されている 。第1期『ウルトラマン』シリーズが第1次怪獣ブームを、第2期『ウルトラマン』シリーズが第2次怪獣ブームを牽引する状況について、その前史、並行して存在した文化と、そのインタラクティブな影響力といった文化史的な状況についてここで明らかにする。また、日本社会のどのような状況をいかにして表象してきたのかという点も併せて触れる。
時代区分は、『ゴジラ』が生まれた1954年から、特撮史のエポックメーキングと捉えられる『ウルトラマン』シリーズが生まれる1966年以前、1966年の『ウルトラQ』以降、シリーズの人気を確立した『ウルトラマン』(1966年~1967年)、『ウルトラセブン』(1967年~1968年)、そしてシリーズ終焉後に、同シリーズのスタッフを継ぐかたちで同じく円谷プロによって製作された後番組『怪奇大作戦』(1968年~1969年)までの「第1次怪獣ブーム」と呼ばれる時代に二分する。
1954年『ゴジラ』以降、1966年『ウルトラQ』以前―空想科学から特撮へ
空想科学(SF)から特撮の時代―『ゴジラ』はどう受容されたのか
/『ゴジラ』(1954)を怪獣映画、特撮の祖とするのはもちろん、不朽の名作として受容する動きは、後年になってからのものといって良い。では同時代評はどうであったのか、新聞紙面を中心に探ると、そこから見えてくるものは「立川文庫的」「科学的であるか否か」という批評眼であった。
→詳細は博士論文「3-2-1 空想科学(SF)から特撮の時代―『ゴジラ』はどう受容されたのか」参照
特撮の盛況とメディアミックス
/『ゴジラ』以外にも怪獣映画、SF映画を量産する東宝に続き、大映、松竹、東映、日活の映画大手4社も映画特撮を公開する。またテレビ特撮も『月光仮面』(1958)を嚆矢に次第に活況となる中では、家電スポンサーが多くつき、それはドラマ性にも影響を与えるものとなった。また、少年を主たる視聴者層としたテレビ特撮は冒険小説や忍者ものなど、既存の児童娯楽の要素を取り入れたり、マンガを原作とする特撮が制作されるのみならず、特撮のコミカライズという逆ベクトルのトランスメディアの様相も見られたりした。あるいは『月光仮面』が映画化されたようにメディアミックスが盛んに行われた。
→詳細は博士論文「3-2-2 特撮の盛況とメディアミックス」参照
1966年『ウルトラQ』以降、1969年『怪奇大作戦』まで―第1次怪獣ブーム
『ウルトラマン』シリーズの原点となる『ウルトラQ』の開始
/アメリカのテレビドラマである『空想科学劇場 アウターリミッツ』や『ミステリーゾーン』の影響を受け、また日本SF作家クラブ参加のもとに企画が成立した『Woo』の作風の上に成立することとなる『ウルトラQ』は、製作途中に怪獣路線で行くことが決まる。SF的、あるいは怪奇・幻想小説的、不条理劇的なドラマと怪獣出現のドラマが混在するのはそのためである。『ウルトラQ』はそれ以前の映画特撮、テレビ特撮の想像力を引き受けつつ、後続の『ウルトラマン』シリーズのみならず、この後の特撮に大きく影響を与えることになる点で、結節点的なコンテンツとなった。
→詳細は博士論文「3-3-1 『ウルトラマン』シリーズの原点となる『ウルトラQ』の開始」参照
『ウルトラQ』―怪獣路線以前のSF的作品
/東宝の『美女と液体人間』(1958年)では全体にエロティシズムが底流するなど、「特撮=子ども向け」という路線が定着していなかった時代の名残で、『ウルトラQ』ではSF性の中に大人の男女のやり取りが描出されるなどした。「1/8計画」、「変身」、「あけてくれ」といった怪獣や巨大生物が出てこないドラマは、『ゴジラ』以降の映画特撮ではなく、SF小説の想像力を引き受けるかたちで展開されたドラマであるといってよい。
→詳細は博士論文「3-3-2 『ウルトラQ』―怪獣路線以前のSF的作品」参照
教育映画、科学映画としての『ウルトラQ』
/SF、あるいは怪奇・幻想的なエピソードと対照的なのが第6話「育てよ!カメ」、第15話「カネゴンの繭」、第18話「虹の卵」など、子どもが主軸となるエピソードである。江戸川乱歩の小説の少年探偵団のように、そして少し前まで少国民として、子どもであっても英雄的な活躍を期待されていたという社会の前史を引き継ぐように、『ウルトラQ』や『ウルトラマン』では子どもが中心となるエピソードが数本存在した。特に『ウルトラQ』では子どもたちの日々の生活の様子や、学校での様子が描写される。これは子どもが中心人物であることで作劇上、必然的なことではあるが、当時、教育の世界のみならず世間一般でも、子どもたちの様子の観察、描写というものに対する関心が高まっていたことと無関係ではないだろう。子どもたちの様子というのは、テレビドキュメンタリーがその恰好の対象とするものであり、社会的な関心事であった。人間の成長の過程を描くという点で、世間の、科学への関心に支えられたものでもあった。「育てよ!カメ」の脚本を書いた山田正弘は、初期の『ウルトラマン』シリーズで脚本を数本担当し、その多くは古くからの少年向け小説のように、子どもたちの活躍を描くものであった。後にNHKの少年ドラマシリーズや、『中学生日記』の脚本も担う山田は、教育ドキュメンタリーの担い手、羽仁進らが名を連ねる、社会運動団体「若い日本の会」のメンバーでもあった。
→詳細は博士論文「3-3-3 教育映画、科学映画としての『ウルトラQ』」参照
『ウルトラQ』の前近代表象
/『ウルトラQ』では。『月光仮面』以降の草創期のテレビ特撮がよく描いていた〈異境〉がたびたび描かれた。次作『ウルトラマン』は近未来が舞台として一応、想定されたことから異境の描出は少なくなったものの、わずかに存在し、その意味でこの2作は、異境を主な舞台として描く従来のテレビ特撮と、異境描出から脱していく以後のテレビ特撮との汽水域に位置付けられる。
『ウルトラQ』第2話では、江戸川由利子が南洋の未開の島を取材しており、第5話では南極が舞台に、第23話では南海の絶島に住む女性と交流する日本人の姿が描かれる。
第23話「南海の怒り」の舞台は、畏怖の存在としての怪獣スダールを守り神として崇めるという前近代的な迷信に支配されている異境である。だがスダールは、現地の人間を襲う凶悪な存在でもあった。日本から漂着した若者は異境のしきたりを破ってスダールを撃退。現地で知り合った女性を救い、二人が結ばれることが予見されてドラマは終わる。このように、前近代的な場としての異境で、迷信や旧弊を破るというドラマは、国内に異境を見出す第7話「SOS富士山」にも顕著で、幼少時に富士山麓の樹海で行方不明となり、野生児として育ったタケルがそこに現れた怪獣ゴルゴスを破る。そして長髪で、粗末な服を身につけていたタケルが床屋で散髪し、スーツに身を包み、新聞社のカメラが向く中、胸を張って歩くところでドラマは終わる。タケルにとって怪獣を葬ることは前近代から脱するための通過儀礼であった。
このドラマが、脱「前近代」を示すことは、『ウルトラマン』第30話「まぼろしの雪山」との比較によってより明確になる。
「まぼろしの雪山」は、ある寒村で行倒れになった母と娘のうち、生き残った娘ゆきをめぐるドラマである。ゆきは炭焼きをやっていた老人に育てられていたが、老人亡き後は身寄りもなく、雪女の娘として村民から迫害されていた。そのゆきを見守っていたのが怪獣ウーであった。しかしリゾート開発されゆくこの村ではウーは「所詮は獣(けだもの)」であり、怪獣が出れば「商売あがったり」になるということで、科学特捜隊に撃退が要請される。最終的にはウルトラマンも現れてウーと対峙するが、ウーは姿を消す。そして雪の中、野ウサギらに見送られるかのように、ゆきは死んでいく 。
近代化する社会の外に置かれたタケルとゆきを描いた「SOS富士山」と「まぼろしの雪山」はともに、メインライターである金城哲夫の脚本であるが、対照的な終わり方である。人々は近代化の内側に身を置くことでしか存在し続けられないことを物語っている。『ウルトラQ』や『ウルトラマン』に描かれる異境は、打ち破られるために設定された前近代的な場所であり、その点でこれらは近代化のドラマであった。
異境の描出は『ウルトラマン』で数編があるほか、他のテレビ特撮でも『怪獣王子』(1967年~1968年)があるくらいで、以後は『変身忍者嵐』(1972年~1973年)のように、時代設定そのものが江戸時代であるといった時代劇のような特撮を除けば、特撮において前近代的な世界観の描出はほとんど見られなくなる。
脱「前近代」は、例えばギャングの不在等にも見られる。『ウルトラQ』では、先述の「育てよ!カメ」のほか、第3話「宇宙からの贈りもの」、第24話「ゴーガの像」で、黒い出で立ちにサングラスというステレオタイプなギャングが描かれているが、このようなギャングの描出は『ウルトラQ』のみの特徴である。『ウルトラマン』第6話「沿岸警備命令」では、ダイヤモンド・キックと呼ばれる宝石密輸団が描かれ、少年たちを絡める点で、冒険小説的な様相を見せるが、彼らはギャングの出で立ちではない。また盗賊、強盗団といった、冒険小説のキャラクター的な存在の描出自体が見られなくなっていく。
→詳細は博士論文「3-3-4 『ウルトラQ』の前近代表象」参照
空想科学の想像力とメタボリズム
/『ウルトラQ』に科学映画的な描出があることを述べたが、その傾向は以後も続く。『ウルトラマン』第16話「科特隊宇宙へ」ではドラマの冒頭で「科学とは何か」、「科学者はどうあるべきか」といったことが示されるが、同作の脚本、監督を担当した飯島敏宏は、そのような自身の想像力の源泉として『子供の科学』を上げている。『ウルトラセブン』第31話「悪魔の住む花」では、ミクロな宇宙ともいうべき異空間として人体が舞台化され、第44話「恐怖の超猿人」では、霊長類の研究所である日本モンキーセンターが舞台となり、ゴールデンライオンタマリンなど幾種類ものサル類の生態が、直接的にはドラマの本筋と関わらないかたちで映される。
また、近未来を作品の時代背景とし、脱「前近代」が進む中では、輝かしい都市化への夢想が作品にはあふれていた。『ウルトラマン』では流線型のメカに加え、それ自体オブジェ的で先鋭的なフォルムの科学特捜隊の基地が存在する。
五十嵐太郎・磯達雄『ぼくらが夢見た未来都市』によれば、建築家にはSFの愛読者が少なくなく、またSFの側も建築家による未来都市への提案に興味を示していたのだという。また、松山秀明が『テレビ越しの東京史 ―戦後首都の遠視法―』で指摘するように、同時代のテレビは近代化する東京を映し続け、結果、未来都市の予想図を視聴者に提供する装置たり得た。このような脈絡を踏まえるなら、幾何学的、オブジェ的なフォルムの科学特捜隊基地、あるいは頻繁に人物の背景に無機質な物体、幾何学模様を置く実相寺昭雄の演出には、建築の前衛的な思想、方法であったメタボリズムを見出すことが可能だろう。
メタボリズムとは新陳代謝の意味で、牽引者の一人、黒川紀章によれば、「抽象的幾何学」という機械の時代の造型的な近代性を引き継ぐものである。つまり、未来都市の具現化の一つと言えるが、それが反転したかたち、つまりディストピアとして映し出されたのが『ウルトラセブン』第43話「第四惑星の悪夢」の無機質な惑星なのである。
→詳細は博士論文「3-3-6 『ウルトラマン』シリーズのメタボリズム」参照
以後、随時追加(2024年~2025年 公開予定)